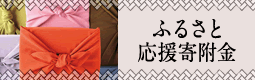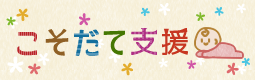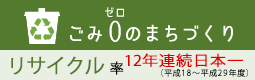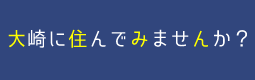ここから本文です。
更新日:2025年4月8日
こども計画
計画の策定にあたって
計画策定の背景
近年の国のこども・子育て支援は、「次世代育成支援対策推進法」(平成17年施行)、「子ども・子育て支援法」(平成27年施行)をはじめとした各種法整備に基づき、これまで各施策・制度が進められてきました。
こどもの健やかな成長を支援するこども・子育て支援の取組のみならず、少子化対策、こども・若者育成支援、こどもの貧困、児童虐待防止対策等こどもを取り巻く多様な環境・課題、社会の変化に合わせ、それぞれ個別の法整備が行われ各種計画の策定や取組が進められてきていますが、少子化の進行、人口減少には歯止めがかかっていないのが現状です。
これに加えて、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による収入の減少が与える貧困世帯での学習環境の悪化、こどもへの虐待件数の増加、ヤングケアラーへの対応、こどもの孤立等の問題に加え、子育て家庭の孤立、女性のL字カーブ問題等のこどもを取り巻く環境は深刻化・多様化しています。
そこで、国は、常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組や政策を我が国の社会の真ん中に据えて、強力に進めていくため、令和5年4月に「こども家庭庁」が発足しました。こども家庭庁は、こども政策の司令塔となり、省庁の縦割りを排し、これまで組織の間でこぼれ落ちていたこどもに関する福祉行政を一元的に担うこととなっています。
同じく令和5年4月から、こどもを権利の主体として位置付け、その権利を保障する総合的な法律として「こども基本法」が施行となり、さらに、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等を行うことを目的として、児童福祉法等の一部が改正(令和6年4月1日施行)されるなど法整備が進められ、令和5年6月13日には「こども未来戦略方針」が閣議決定され、児童手当や育児休業給付の拡充、保育の拡充など少子化対策の更なる強化も進められています。
なお、令和5年12月22日には、こども基本法に基づき、こども政策を総合的に推進するため、政府全体のこども施策の基本的な方針等を定める「こども大綱」を閣議決定しました。
この「こども大綱」は、従来の「少子化社会対策大綱」、「子供・若者育成支援推進大綱」及び「子供の貧困対策に関する大綱」を一つに束ね、一元化するとともに、さらに必要なこども施策を盛り込むことで、これまで以上に総合的かつ一体的にこども施策を進めていくこととしています。
また、「こども未来戦略」、「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの100か月の育ちビジョン)」などもあわせて閣議決定されています。
計画の位置付け
前期計画である「第2期大崎町子ども・子育て支援事業計画」は、子ども・子育て支援法第61条第1項に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」及び次世代育成支援対策推進法第8条に基づく「市町村次世代育成支援対策行動計画」として策定していました。さらに、「新・放課後子ども総合プラン」及び「子どもの貧困対策計画」についても、包括的に盛り込んでいました。
新たな計画となる「大崎町こども計画」では、国のこども大綱やこども基本法を勘案し、前期計画に新たに子ども・若者育成支援推進法第9条に規定する市町村子ども・若者計画、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第10条に規定する市町村計画を包含するとともに、生育基本法に基づく母子保健を含む成育医療等に関する計画を包含し、こども施策を総合的に推進するものです。
また、本計画は「まち・ひと・しごと、世界の未来をつくる、循環のまち」を目指す大崎町総合計画を上位計画とした「大崎町地域福祉計画」の部門別計画となります。計画の策定にあたっては、各部門別計画と一定の整合性を保持し、連携を図ります。
計画書ダウンロード
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556