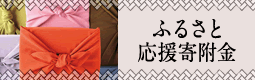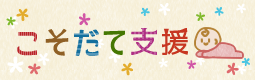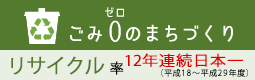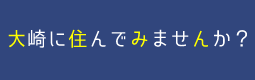ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
介護保険制度のQ&A
介護保険制度とは?
本格的な高齢社会が進むなか、介護を必要とする人は増加し続けています。また、核家族や少子化などにより介護をする若い人たちの数が減るなど、家族だけで介護をすることは難しくなってきています。
介護保険は、介護が必要な人や家族の負担を社会全体で支え、介護が必要となっても住み慣れた地域で、できる限り自立した生活を送るためにつくられた制度です。
介護保険制度では?
- 家族の介護の負担を軽減し、介護を社会みんなで支えます。
- 医療や福祉の介護サービスを一体的に利用できます。
- 自分で選んだサービスを、多様な事業者から効率よく利用できます。
- できる限り自宅や地域の中で自立した生活を送れるよう支援します。
介護保険の仕組みは?
- 40歳以上のみなさんが被保険者となって介護保険料を納め、介護が必要となったときには費用の一部を支払うことで介護保険のサービスを利用できます。
第1号被保険者(65歳以上の人)
- 介護や支援が必要となったときに、町の認定を受けてサービスが利用できます。どんな病気やけがが原因で介護や支援が必要になったかは問われません。
第2号被保険者(医療保険に加入している40歳~64歳の人)
- 特定疾病により介護や支援が必要となったときに、町の認定を受けてサービスが利用できます。交通事故や転倒などが原因の場合は、介護保険は利用できません。
サービス利用の手続きはどうするの?
- 介護サービスを受けるためには「要介護認定」を受けなければなりません。
- 介護認定は町の介護保険窓口に申請します。
介護サービスを受けるにはどうするの?
「非該当」を除き要介護認定が決定したあとは、以下のとおり介護サービスが受けられます。
要介護1~5の認定者
- 在宅サービス、地域密着型サービス
在宅でのサービスを希望される場合、原則として本人や家族が居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して、本人の心身の状況や利用希望などを考慮して最も適した介護サービス計画(ケアプラン)を作成して、本人等の了解を得た上でサービスが提供されます。
- 施設サービス
施設サービスを希望される場合、原則として本人もしくは家族が直接施設に申し込んで入所・入院します。入所・入院すると施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、この計画に基づきサービスが提供されます。
要支援1・2の認定者
地域包括支援センターの保健師等が本人の心身の状況や利用希望などを把握、分析後、支援メニューを検討して、介護予防のためのケアプランを作成します。
介護サービスの内容は?
在宅サービス
- 訪問介護
自宅にホームヘルパーなどが訪れ、排せつや入浴などの身体介護、そうじ洗濯などの生活援助を行います。また、看護士やリハビリテーションの専門職が自宅を訪問して行う看護やリハビリもあります。
- 通所介護
日帰りで通所介護施設・介護保健施設などに通って、日常生活上の支援、機能訓練や食事、入浴、リハビリテーションのサービスを受けられます。
施設サービス
自宅では自立した生活が困難な人に対し、介護保険施設へ入所して介護・保健・医療等の必要なサービスを提供します。
施設サービスは、要介護1~5の認定を受けている人が利用できます。(要支援1・2の人は保険給付の対象外)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ※新規入所は原則として要介護3~5の人が対象
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護医療院
地域密着型サービス(大崎町が指定しているサービス)
住み慣れた自宅や地域でできるかぎり生活を続けられるように、地域ごとの実情に応じた柔軟な体制で提供される介護サービスで、平成18年4月から創設されました。
※大崎町に住所のある方が対象です。
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
入居定員が29人以下の介護専用型特定施設(有料老人ホームやケアハウスなど)に入居しながら、入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練などを受けるサービスです。
- 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の状態にある高齢者が、家庭的な雰囲気の中において9人で共同生活を行いながら、介護スタッフによる食事、入浴、排泄など日常生活の支援や、機能訓練などを受けるサービスです。
要介護1~5、要支援2の認定を受けている方が対象となります。
- 地域密着型通所介護
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の介護や、生活機能向上のための世話を日帰りで行います。
平成28年4月1日より、利用定員が18人以下の通所介護事業所は地域密着型通所介護事業所へと移行しました。
利用者負担はいくら?
- 介護サービス計画(ケアプラン)にしたがって各種のサービスを利用した場合、利用者はかかった費用の1~3割(所得等に応じて判定)を負担します。
介護保険料は?
65歳以上の方(第1号被保険者)
- 納め方
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が、年額18万円以上の人は年金から天引きし、それ以外の方は、町に個別に納めます。
- 保険料
市区町村の介護サービスの水準により異なり、所得に応じて段階的に設定されます。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
- 納め方
医療保険の保険料に上乗せして納めます。
- 保険料
加入している医療保険によって計算方法が異なります。
介護保険制度は、40歳以上の国民全員が保険料を負担します。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556