ここから本文です。
更新日:2025年12月26日
町民税(個人)
住民税について(住民税は6月に賦課されてから、指定された納期限内に町へ納付します。)
- 所得税は、毎年1月1日から12月31日までの所得に応じて、確定申告等で国へ納付します。(原則、3月15日が納期限です。)
- 申告会場へ来る前に「収支計算書」「控除証明書類」等の不備・不足がないか、事前のご確認をお願いいたします。
- 原則として「収支計算書」は作成後にお越しください。
- 申告会場において、収支計算書を確認・作成する時間が長くなると、他の方の申告待ち時間に影響がありますのでご了承ください。
- イータックス(e-TAX(外部サイトへリンク))をご活用ください。
- チャットボット「ふたば(外部サイトへリンク)」で24時間のお問い合わせがで来ます。
- タックスアンサー(外部サイトへリンク)(よくある税の質問)もご確認ください。
- 定額減税特設サイトのご案内(外部サイトへリンク)
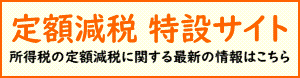 (外部サイトへリンク)
(外部サイトへリンク) - 税務署の内部事務のセンター化について(外部サイトへリンク):参考
- 紙による確定申告書(所得税)の提出先(郵送先)が変更されました。ご確認ください。
住民税とは
(例年2月中旬から3月15日を目途に申告会場(PDF:104KB)を準備しています。)
- 1月1日に住所を有していた市町村において、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得をもとに住民税申告を受け付け、6月に税額が決定されます。
- 一般的に県民税と町民税を合わせたものを住民税といいます。
- 住民税は、一定の金額を負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」があります。
- 個人住民税申告の電子化に係る特設ページ(外部サイトへリンク)
- 個人住民税:eLTAX申告通知ポータルTOP画面(R8.1.5以降、開始される予定です。)
- スマートフォンやパソコンで、マイナンバーカードを利用して、eLTAX(エルタックス)※のホームページ、マイナポータル及び市ホームページを経由し個人住民税の申告手続きが開始される予定です。
住民税がかからない人
| 均等割 | 所得割 | |||
|
どちらも非課税 |
|
|||
|
どちらかが非課税 |
扶養親族がいない人 合計所得金額が 38万円以下 |
扶養親族がいる人 28万円×(扶養親族数+1) +26万8千円 1人:28万円×2+26万8千円 =828,000円 2人:28万円×3+26万8千円 =1,108,000円 3人:28万円×4+26万8千円 =1,388,000円 ※合計所得金額が上記の金額以下であれば、均等割は課税されません。 |
扶養親族がいない人 総所得金額が 45万円以下 |
扶養親族がいる人 35万円×(扶養親族数+1) +42万円 1人:35万円×2+42万円 =1,120,000円 2人:35万円×3+42万円 =1,470,000円 3人:35万円×4+42万円 =1,820,000円 ※合計所得金額が上記の金額以下であれば、所得割は課税されません。 |
税額の計算方法
- 均等割額【 県民税(1,500円)+町民税(3,000円)+森林環境税(1,000円)=5,500円 】
- 東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度まで個人住民税の均等割額に1,000円(町民税500円・県民税500円)が加算されていました。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき,森林環境譲与税の財源として,令和6年度から個人住民税の均等割額に年額1,000円が加算されました。
- 大崎町における森林環境税(森林環境譲与税)の使途の公表について(参照)
- 鹿児島県みんなの森づくり県民税構想〔第5期〕について(外部サイトへリンク)(令和7~11年度)
| 均等割 | 平成25年度まで |
平成26年度から 令和5年度まで |
令和6年度から |
| 町民税 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
|
県民税 ※みんなの森づくり県民税 500円含む |
1,500円 | 2,000円 |
1,500円 (令和7~11年度まで延長) |
| 国税(森林環境税) | なし | なし | 1,000円 |
| 合計 | 4,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
- 所得割額=課税標準額(所得金額-所得控除額)×税率(10%) ー 税額控除
- ※税率(10%)は、県民税4%と町民税6%の合計の税率です。
所得とは
- 所得とは収入金額から必要経費を差し引いたもので、税額計算の元となるものです。
- 所得=収入金額 ー 経費
所得の種類と計算方法(確定申告等の参考)(外部サイトへリンク)
|
所得の種類 |
所得金額の計算方法 |
||
|---|---|---|---|
|
1 |
利子所得 |
公債、社債、預貯金などの利子 |
|
|
2 |
配当所得 |
株式や出資の配当など |
|
|
3 |
不動産所得 |
地代、家賃、権利金など |
|
|
4 |
事業所得 |
事業をしている場合に生じる所得 |
|
|
5 |
給与所得 |
サラリーマンの給料など |
|
|
6 |
退職所得 |
退職金、一時恩給など |
|
|
7 |
山林所得 |
山林を売った場合に生じる所得 |
|
|
8 |
譲渡所得 |
土地などの財産を売った場合に生じる所得 |
|
|
9 |
一時所得 |
臨時・偶発的なもので対価性のない所得 |
|
|
10 |
雑所得 |
公的年金等、原稿料など他の所得に当てはまらない所得 |
|
所得控除とは(外部サイトへリンク)
- 所得控除とは、住民税を計算する際に所得から差し引かれる金額です。詳細は、下記の「控除の種類」に掲載されております。
- 税額控除とは、住民税を計算した後に、税額から差し引きされる控除です。
- 控除の種類(外部サイトについては、国税庁の所得税に関するタックサンサーから参考としてみることができます。控除額については、所得税と住民税では異なりますのでご留意ください。)

|
種類 |
控除の対象 |
|
|---|---|---|
|
1 |
雑損控除 |
災害等により損失を受けた場合の控除 |
|
2 |
医療費控除 |
|
|
3 |
社会保険料控除 |
|
|
4 |
小規模企業共済等掛金控除 |
|
|
5 |
生命保険料控除 |
|
|
6 |
地震保険料控除 |
|
|
7 |
寄附金控除 |
都道府県、市町村または住所地の都道府県共同募金もしくは日本赤十字支社の支部に対して寄附を行った場合の控除、都道府県及び市町村が条例で定めた寄附金の控除 |
|
8 |
障害者控除 |
|
|
9 |
寡婦控除 |
|
|
10 |
ひとり親控除 |
|
|
11 |
勤労学生控除 |
|
|
12 |
配偶者控除 |
|
|
13 |
配偶者特別控除 |
生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)を有する納税義務者で、配偶者の所得に応じた金額を控除します。 |
|
14 |
扶養控除 |
扶養親族がいる場合の控除(平成24年度適用から年少扶養控除(16歳未満)を対象とした年少扶養控除はありません。) |
| 15 | 特定親族特別控除 |
居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者を除きます)で合計所得が58万円超123万円以下の人を言います。 (注)収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得が58万円超123万円以下となります。 |
|
16 |
基礎控除 |
令和7年分以降の所得税と住民税の基礎控除額は改正内容が異なりますのでご留意ください。 |
納税の方法
1 普通徴収
- 町から納税義務者へ納付書、納税通知書を送付します。
- 納期は、通常6月、8月、10月、12月の4回です。(eL-QRコードによるキャッシュレス納付をご活用ください。)
2 給与特別徴収
- 給与所得者へは特別徴収税額通知書により給与の支払者を通じて通知され、毎月の給与の支払の際に天引きされます。
- 給与の支払者からの届け出が必要です。
- 納期は6月~翌年5月までの12回です。
※年の途中で退職した場合、下記以外は、普通徴収となります。
- 新しい会社で特別徴収の手続きを行う。
- 退職手当などからまとめて残額を特別徴収する。
- 1月1日~4月30日の期間で退職した場合、給与または退職金により特別徴収する。
- 65歳以上の公的年金の所得に係る住民税は、税額決定通知書により市町村から通知され、年6回(偶数月)の公的年金の支払いの際に天引きされます。
- 引き落とし(特別徴収)の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」です。
その他
1 納期限について
3 救済制度
住民税の賦課決定や滞納処分などに不服のある方は異議申し立てをすることができます。
- (1)賦課決定に対して
決定の通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内。 - (2)督促に対して
督促に欠陥があることを理由とする滞納処分についての異議申し立ては、差し押さえにかかる決定の通知を受け取った日の翌日から起算して30日を経過した日まで。 - (3)不動産等の差し押さえに対して
不動産等についての差し押さえに欠陥があることを理由とする滞納処分についての異議申し立ては、その公売期日まで。
4 地震等の被害を受けられた方へ
- (1)申告,納税などができない方は申請していただければ、期限の延長ができます。
- (2)事業用資産に損害がある場合、3年間繰り越して損失の計上ができます。
- (3)住宅や家財などに損害がある場合、損害の額を申告し、雑損控除の適用を受けることにより、個人住民税の一部または全部が軽減されます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556
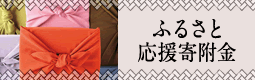

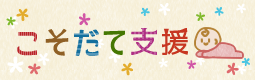
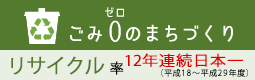
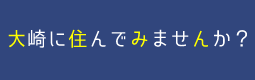

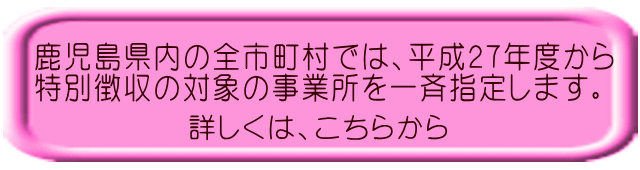 (外部サイトへリンク)
(外部サイトへリンク)